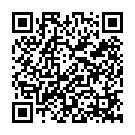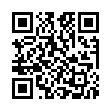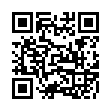東雲特許事務所の特許調査(先行技術調査・先行特許調査)
特許を出願する前に行う特許調査をここまでやっています
特許を出す前には、どのような関連特許があるか、特許調査を行うことが重要です。このような特許調査は、先行特許調査・先行技術調査・技術動向調査などと言われます(名称はさほど重要ではありません。以下単に特許調査と言います)。
特許調査は、大手の企業であれば自社内で行えますが、個人発明家・小規模事業者などの場合、ご自身で行うことは難しいでしょう。そこで、弊所で特許調査を行うことができます。以下のように、弊所の知見を生かして、ここまでやるのかという特許調査を行っています。
特許調査の目的
弊所の特許調査は、以下の目的のために行います。
①特許を出すべきか出さないべきかを判断する
②あなたの発明をどのように改良すれば特許になる可能性が上がるかを判断する
③特許出願書類をより良いものにする
東雲特許事務所の特許調査の特徴
一般的な特許調査の手法は、別の項でも説明していますので、本記事では弊所の特徴を挙げます。
(1)特許庁に設置された「高度な調査が可能な端末」を用いて行います。審査官と同様の環境で特許調査を行います。
(2)調査漏れを可能な限り防ぐため、所長弁理士(元特許審査官)を含めた2人以上で多重チェックを行います。
(3)調査開始後ただちに関連特許が発見された場合、その旨を報告し、特許調査をキャンセルすることがあります(着手金を頂いている場合は返金します)。
(4)調査の途中で、必要に応じて、途中経過をフィードバックし、調査の方向性を再確認します。
(5)特許調査の結果、特許になる可能性がほとんどない場合は、特許を出さずにいったん保留にすることを、積極的にご提案します(目的①)
(6)特許調査の結果に基づいて、どのような改良を行えば特許になる可能性が上がるか、アドバイスします(目的②)。
(7)あなたの発明と先行特許との違いを熟知している所長弁理士が、そのまま特許出願書類を作成します(目的③)。
特許調査をここまでやる理由
上記特徴(1)~(4)、(7)は、特許調査を外部に委託することなく、弊所内で行うことで実現しています。
上記特徴(5)~(7)は、調査依頼主であるあなたのメリットになることは言うまでもありませんが、もちろん弊所のメリットにもなりますし、さらには、特許庁の審査官のメリットにもなります。審査の過程でのやりとりをできるだけ軽減できるからです。
なお、上記特徴(5)については、特許の出願のご依頼を頂けなくなる場合があるということで、必ずしも弊所のメリットになるとは限りませんが、それでもお客様との信頼関係構築というメリットはあります。
いかがでしたでしょうか(自社内で特許調査を行うことが難しい企業様へ)
少なくとも当面の間は、弊所の知見を生かして、ここまでやるのかという特許調査を行ってまいります。
ただあまりハードルを上げてしまうのもなんですので、そのうちこの記事の一部が削除されているかも知れません(笑)。とは言っても、(1)~(7)はどれも削除できない内容ばかりですので、やはり、同時期にあまりたくさんのご依頼を受けないことで対応するほかありませんね(審査官時代の激務の経験を生かしはしますが・・・)。ぜひお早めにご依頼ください。
なお、冒頭で、個人発明家・小規模事業者などの場合、特許調査をご自身で行うことは難しいと述べましたが、中規模以上の企業様であっても、自社内で特許調査を行うことが難しい場合は、特許調査のご依頼を受けられる場合があります。お気軽にお問い合わせください。
 東雲特許事務所
東雲特許事務所