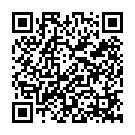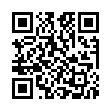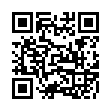シフト補正の微妙なお話し(1)
シフト補正の微妙なお話しです。
【請求項1】・・・処理装置。
【請求項2】・・・請求項1に記載の処理装置。
【請求項3】コンピュータを,請求項1又は2に記載の処理装置として機能させるためのプログラム。
【請求項4】請求項3に記載のプログラムを記録した記録媒体。
プログラムや記録媒体をおまけ的に付けることって昔は結構あったように思えます。
ところが平成19年改正以降は・・・
請求項4までいってもSTFが発見できない場合,拒絶理由通知には,「請求項4に係る発明のうち・・・に補正することを検討されたい」のように記載される?
普通に読めば,え~記録媒体しか権利化できないの~,ということになりそうですね。
う~ん・・・
いまこちらの勉強会で出ている一つの対策は、
同じカテゴリーで発明の名称が異なるクレーム(装置とプログラム、レンズとカメラなど)を入れる場合は、請求項1のみ引用する(請求項1のみと技術的特徴を同じにする)のはどうかというものです。上記例では、請求項3は請求項1だけを引用する。そうすれば、STFの判断は請求項2で終わりですから、シフト補正の基準は請求項2になって、処理装置での権利化も可能です。
必要であれば、名称の異なる発明については、審査が進んで特許される部分が分かってから、従属項を追加することも可能かと思います。
他の対策としては、出願時には名称の異なる発明のクレームは作らないという案もあります。こちらも、必要であれば、特許される部分が分かってから従属項の追加が可能かと思います。ただいずれの対策も、拒絶理由が一度も通知されず一発特許された場合に、微妙ですね。
はじめに戻って、上記の「記録媒体しか権利化できない」については、もしかしたら平成19年改正の想定外のことなのかも知れません。シフト補正の趣旨を考えれば、実務的には処理装置に補正しても大丈夫なこともあると思います。でも出願人側はそんな危険を冒せません。審査基準の充実など早めに対策を練ってほしいものです。
(元特許庁審査官 弁理士 田村誠治)
 東雲特許事務所
東雲特許事務所